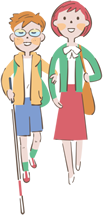第79回全国視覚障害者福祉大会(宮城・仙台大会)のご案内 その2
理事長 宇和野康弘
全国大会の概要は既にみなさまにお知らせしましたが、各会議等の説明と大会に対する参加ご協力のお願いをいたします。
大会の会場は江陽グランドホテルの4階と5階を使用します。
1日目は、シンポジウム・開会式・分科会・懇親会、2日目は式典・大会議事が行われます。また、二日間を通して防災関連の展示・福祉用具の展示、い・卓球の体験も行われます。
1日目10時からのシンポジウムでは地域交通の問題をテーマに、国土交通省・鉄道会社学識経験者などからこれからの取り組みについて語っていただく予定です。
12時45分からは開会式が始まりますが、それに先立って、仙台ガブリエリブラスが歓迎演奏をします。
13時30分から三つの分科会が並行して行われます。
(1)生活分科会
障害福祉サービス全般、意思疎通支援事業、同行援護、補装具・日常生活用具、歩行訓練、医療と福祉の連携、身障者手帳、年金、マイナンバーカード、医療、高齢者問題、教育、点字郵便、盲導犬、災害・防災対策、その他
(2)バリアフリー分科会
道路・鉄道・自動車等交通の安全対策、施設全般のバリアフリー、情報保障、ICT関連機器のアクセシビリティ、無人化・デジタル化に対する代替手段の確保、その他
(3)職業分科会
あん摩・マッサージ・指圧、鍼、灸関係、マイナ保険証、ヘルスキーパー、重度障害者等に対する通勤や職場等における支援、雇用・就労に対する支援、合理的配慮の提供、その他
18時からの懇親会では、すずめ踊りの出演を予定しています。
2日目は、9時45分から式典が執り行われます。視覚障害者福祉に功労のあった方々への表彰・感謝状をお送りした後、主催者からの挨拶、宮城県知事・仙台市長など来賓の祝辞があります。その後、大会議事に移り、1日目の分科会での討議を受けて大会宣言案と決議案の承認を行い閉会となります。
大会の参加申し込み一次締切は2月末ですが、地元からの参加については3月末まで申し込みは可能です。
全国から参加者を迎え、交流を図る貴重な機会ですので、一人でも多くの方にご参加いただきたいと思います。