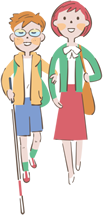日視連令和6年度中央情勢報告から(1)
日視連から加盟団体に竹下会長による令和6年度中央情勢報告の音楽CD版とテキスト版が送られてきました。希望者には郵送またはメールでお送りしますのでご連絡ください。また、音楽CD版と同じ内容の音声ファイルをYouTubeで公開しています。キーワードで「日視連 中央情勢報告 ユーチューブ」で検索できます。
ここでは、報告の要旨を掲載いたします。なお、内容は令和6年11月2日時点のものです。
1.日視連の活動について
日視連の会員の皆さん、そして全国の視覚障害者の皆さんに日視連の活動を報告させていただきたいと思います。日視連活動のスタート点ともなる全国視覚障害者福祉大会は6月2日、3日に、熊本市において500人を超える参加を得て開催されました。ここで皆さんに議論いただいた要求内容あるいは宣言、決議を基本に陳情項目を整理しまして、8月に4日間をかけて各省庁に陳情活動を行い、その要求に対する国の考え方をお聞きするなどしています。我々の声で直ちに制度が改善されるということにはなかなかなりませんけれども、この活動を繰り返す中で、徐々にではありますが目に見える形での改善があったり、非常に微妙な形での修正があったりということの積み重ねの中で、我々の日々の生活が一つずつよくなってきているのかなと思います。
2.協議会の活動について
今年は女性協の大会は、9月の4日、5日に香川県の高松市で、青年協の大会は9月15、16日に大阪市で行われました。両大会とも、直面の課題やこれからの組織の在り方など熱心な討議が交わされていました。日視連にはこの二つを含めて五つの協議会がありますが、年々会員数の減少や役員の担い手不足など難しい問題を抱えてきていることから、3月に執行部と協議会役員が今後について意見交換しました。場合によっては組織の見直しが必要になるかもしれません。
3.音声ナビゲーションシステムについて
3月に音声ナビゲーションシステムを使った歩行の安全確保について懇談会を開きました。晴眼者の歩きスマホと区別する合理的な理由、視覚障害者が事故にあわないための安全な使用法、交通ルールと法律上の課題などについて検討しました。
4.弱視問題の取り組みについて
弱視は見え方、それに応じた工夫や援助法など十人十色ともいわれるほど異なるために、取り組みのむずかしさがあります。日視連の弱視部会はこれまで弱視の理解・啓発用のリーフレットの作成、動画の配信などを行ってきました。9月の総会ではこれまでの取り組みを充実させるとともに、活動をさらに広げるために地域で関係者と連携してセミナーなどを開催していく必要性が示されました。
5.将来ビジョンの見直しについて
日視連では組織や活動の方向性を示した将来ビジョンというものを作っています。しかし、これがどんどん進む社会にそぐわなくなりつつあるため見直しの議論を続けています。一昨年国連から日本政府に示された障害者権利条約に基づく総括所見から見た将来の障害者福祉の在り方、視覚障害者の教育、施設と地域との関係、職業などの分野について日視連としての考え方を整理してみなさんにお示ししたいと思っています。
6.能登半島地震に関する支援について
私は能登半島の輪島で生まれ育った人間です。元日の大地震で実家は全壊し、さらに9月の豪雨で地域は大きな痛手を受けました。日視連としては日本盲人福祉委員会に設置された災害支援対策本部の皆さんとともに能登半島における被災視覚障害者への支援を進めてきています。全国の皆さんの協力を得て、義援金として1000万円を超える多額のお金を頂いて、これを能登半島を中心とした石川県の被災視覚障害者に配分してきております。被災した障害者がどういう状況にあって、どんな支援を受けているかの情報は残念ながら自治体からは得られないため、日本障害フォーラム(JDF)が能登の真ん中の七尾市に設けた支援本部を拠点に日本盲人福祉委員会のみなさんの力を得て個別訪問による支援を続けているところです。これからも引き続き支援を続けていきますので、みなさんのご協力もよろしくお願いいたします。